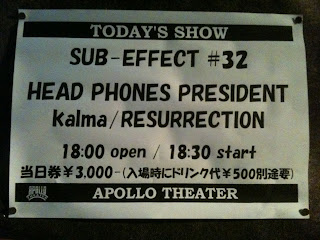先週、HEAD PHONES PRESIDENTが4年半ぶりにオリジナル・フルアルバムをリリースした。
5月下旬から先行配信されていたこの新作『Stand In The World』は、これまでになくキャッチーで聴きやすい多彩な楽曲がつまった、HPPにとって大きな転換点となるであろう「会心の傑作」となっている。
Stand In The World
5月22日24時、急遽iTunesより先行配信の始まった本作をいちはやく聴いた感想を引用する。
(Twitterで6連投となったものを、いくらか削った上でまとめなおした)
かつてなくキャッチーで多彩な楽曲群を配したこの新作において、メタルやヘヴィロックの定型により接近しつつ、しかし完全に逸脱するという離れ技をHPPは披露した。これは新しい音楽だ。 もっとも特徴的に思われるのは、ヘヴィネスの様相に変化が聴きとれることだ。これまでは、不条理に対する「なぜ?」を倫理的な怒り・やり場のない哀しみとして表現していた。そこに、それを前提として「ならば、どうするか?」というアクティヴなニュアンスが付加されたように感じたのである。言うなれば、「Why」から「How」へ、マイナスからプラスへ、という変化である。いや、まだそれは混在している。しかし、この新作においては「重さ」が「重苦しさ」に留まってなどいない。むしろ、快活さすら感じとれる瞬間も多いほどだ。また、HPP独特の「無国籍情緒」とでも呼べそうな、詩情ある儚さもより繊細な襞を獲得したように思う。いや、繊細さだけではない。ピアノをバックにAnzaが独唱する曲においては、そこに力強さすら加味されていた。また、各メンバーが素晴らしい躍進を遂げている。Anzaは持ち前の歌唱にさらなるダイナミズムと彩りを、Hiroは異様な速度で詰め込まれたソロと奇矯なリフ/展開を、NarumiとBatchは楽曲の「土台/接着剤」以上のフレージング/存在感を、それぞれもたらした。会心の傑作だ。
この時点では1回半しか聴いていなかったわけだが、いまも感想の大筋は変わらない。
以下に、こうした印象をもたらした楽曲群それ自体と、本作における「転換」の内訳について、
わたしなりに感じ、考えたことを詳述する。やや煩雑なところもあるとは思うが、そこはご容赦願いたい。
(簡単なものをアマゾンのレビューに書いたので、それで十分という方はこちらをどうぞ。)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
端的に言うと、本作のわかりやすさ/聴きやすさは「歌詞の変化」に拠るところが大きい。
(「《歌詞の変化》を導いた変化」については、楽曲について語りつつ後述する)
歌詞は変わらず英詞なのだが、今回は意図的に「わかりやすい」単語を選んだと言う。
これを裏返すと、今までは意図的に「わかりにくい」単語を選んでいたということだ。
実際、そうだった。それどころか、ほとんど「壊れた」英詞が特徴ですらあったのだ。
そこに、Anza語が加わる。大体が英単語からなる、しかし意味を為さない音節群が…。
わたしはこれまで、HPP最大の特色のひとつである「Anza語」について言いそびれてきた。
何度か、そこに踏み込みそうになって戸惑ったり、また踏み込もうとして失敗したりと、
一進一退と言うのは憚られるほどの惨敗っぷりを隠蔽しつつ、書き進めてきた経緯がある。
しかし、今度ばかりは歌詞の在り方とその機能について、どうしても語らねばならない。
言語学、言語哲学、認知論、詩学(文学)、音楽学に跨ったこの問題をさらりと流しつつ、
「なぜ、そのように歌われなければならなかったのか」、わたしの考えを書いていく。
「Anza語」とは、早い話が「スキャット」に他ならない。
しかし、つけ加えねばならないのは、それはただのスキャットとは異なることだ。
ふつう、スキャットは「ららら」「るるる」といった単音によって構成されるか、
「ダバダ」「ドゥビドゥバ」といった反復される音節によるかの、いずれかである。
Anza語にもそういった「ただの音」は登場するが、基本的には英単語を用いている。
(いや、その比率が次第に高くなっていったと言った方がより正確であろう。
試みに"abiso"(2003)、"Puraudis"(2007)、"Sixoneight"(2009)と聴き継いでみるといい。)
そのため、ライブで彼女のAnza語による即興的な歌唱や曲間における独語を聞くと、
「自分には聞き取れないが、きっと流暢な英語を話しているのだろう」と思いがちである。
しかし、Anzaは英語を話せない。英語を使っているのではなく、その音をなぞっているだけなのだ。
言葉の上っ面である、言葉の「響き」をなぞること。
言葉を「ただの音」として取り扱い、声を楽器として扱うこと。
それゆえ、かろうじてAnza語を「スキャット」と呼ぶことができるのである。
それはメロディを、そのメロディに託された思いを音声化するための「依り代」でしかなく、
必要とされるのはその言葉(←言語未満を含む)の「響き」であって、「意味」ではないのだ。
(ただ、その「意味」から思い浮かべた単語を歌う、ということもたくさんあるだろう。)
言葉(言語)には、その音という「外側」と、その意味という「内側」がある。
人間は社会化されるにつれ、音=外殻を触知することなしに意味を認識できるようになる。
ゆえに、(意味を間違って覚えていようが)ある言葉を聞いたらその意味をすぐさま認知する。
HPPが、と言うより、Anzaが避けたかった(と思われる)のが、この社会化された「意味」だった。
(そもそも、「意味」とは社会性そのものである。社会が変われば意味も変わり得る。)
どんな言葉も、使い古され手垢にまみれたがゆえの「陳腐さ」から免れ得ない。
もちろん、言葉単体だけでなく、文章(フレーズ)単位でも事態は同じである。
そうした言葉の「意味」が、Anzaの思い/ヴィジョンを損ねて「陳腐」にしてしまう。
大切な思いが、ありきたりで平凡なそれへと「誤解」されてしまうことへの不安。
それならば、言葉の「意味」を放棄し、その「響き」だけを使うようにしてしまえばいい。
Anza語が要請された理由の少なくともひとつは、以上のようなものであったかと思う。
だが、それだけではない。HPPの歌詞において、Anza語はほんの一握りの割合しか占めていない。
ここからが重要なのだが、英詞にNarumiが力を貸すようになってから、更に捻りが加わったのだ。
それ以前も、どちらかと言うとぎこちない英語(直訳調、逐語訳的な英語)による歌詞が散見されたが、
そうした訳のぎこちなさとは違った「不自然な英語」を歌詞として採用するようになったのである。
話は『folie a deux』リリース時のインタビューに遡る。BURRN!2008年1月号に掲載されたものだ。
Anzaはここで、Narumiが「Anza語を英語にできると言ったから任せた。そしたら本当にできてた」
といった趣旨の発言をしているのだが、わたしは当時、これを読んでこう思ったのだ。
「Anzaは実は英語ができたのか。そうでなければジャッジできない。歌詞が楽しみだ」と。
しかし、その歌詞を読んで大いに面食らった。ほとんどわからないのである。知らない単語もあった。
わたしは一応、比較的英語が得意な方である。たいていは読めばわかる。聞いてわかることすらある。
でも、これはわからなかった。敢えてわかりにくくしているとしか思えなかった。そして思い当たった。
英詞なのに、どうゆうわけかAnza語に聞こえはしないか、と。
これは、Anza語の音とリズムを残したまま、それを英語に置き換えた歌詞なのではないか、と。
このことを評して「(Narumiの英訳が)本当にできてた」とAnzaは言ったのではないか、と。
そう思ったら、途端に理解できた。歌詞の「意味」ではなく、その機能が、である。
この、NarumiによるAnza語の英訳を、ここでは「Anglish」と造語しておこう。
Anglishの要点は上記の通りなのだが、その機能についてまとめておきたい。
Anglishは十全な英語ではない。むしろ、あえてそこから離れようとしている。
ゆえに、パッと聞いた限りでは何を言っているのか判然としない(部分が多い)。
単語のチョイスや文章の構成やリズムが、英語として不自然だからだ。
というのも、Anza語がそうであったように「意味の重力」を懸念しているからだ。
狙いは、英語として自然な定型句を連ねることによって導かれてしまう陳腐化を避けること。
しかし、それだけではなかった。
歌詞とは「歌われる言葉」であり、メロディないしリズムと不可分である。
だから、ここには意味作用だけでなく「音楽的な定型(句)」という重力が、
すなわち、「よくあるフレーズ=メロディ≒歌詞(意味)」という陳腐さが、
多重化されて横たわっていたのであり、それもまた避けねばならなかったのである。
そのため、歌詞には難解な単語や奇妙なフレーズが頻出した。文法の無視もいくらかある。
この傾向は『Prodigium』で頂点を迎えた。あれを一読して理解できるひとなどいないだろう。
Anza語とAnglishの混淆も進んだ。だから、"Sixoneight"はそのどちらともつかなくなっていたのだ。
英単語の比率が増したAnza語と、難しい単語/奇妙なフレーズによるAnglishの接近。
ここへきて、Anza語とAnglishはその機能においてほとんど同等の働きを示すようになった。
それだけに、『Pobl Lliw』の出方が気になった。新曲の歌詞をどうするか、という点が。
結果、"Reset"以外の新曲(及び未発表曲)は歌詞が収録されなかった。Anza語だからだ。
しかし、その三曲("Sand"、"Hello"、"Col Delon")はAnglishにも聞こえる。
やはり、その同質化に違いはなかった。なお、"Reset"もAnglishである。
(念のために言っておくが、全編が聞き取り/読み取りにくいわけではない)
こうした歌詞を採用する強みは、個性が強調される点と、歌う当人の表現における自然さである。
HPPにとって絶対的な存在であるAnzaがそう歌うことで、表現により深みが刻まれることとなった。
一方で、普遍性/社会性を失い、理解される度合いを狭めてしまうきらいも同時にあった。
YouTubeのコメントに、外国人の「彼女は何語で歌っているのか?」という書き込みがあった。
また、たとえ単語が英語であったとしてもAnglishであるがゆえの誤解もあったかもしれない。
英詞を「書けない」、英語に「聞こえない」、英語が「できない」というふうに。
「なにを言っているのか/歌っているのかわからない」ことはよくある。
声に出される/歌われるその言葉が、母語ではない言語の場合がそれだ。
ただ、それでもひとはそれが「ナントカ語」だろうと見当をつけることができるし、大抵そうする。
また、それが未知の言語であったとしても、それが言語であることくらいは(なぜか)認識できるのだ。
しかし、仮にその言葉が「壊れて」いたら、必ずしも言語として認知するとは限らない可能性がある。
意識的/無意識的とを問わず、「なにかがおかしい」と察知する。つまり、違和感を抱くことになる。
Anglishを導入したことでより表現の精度を(逆説的に!)高めたHPPであったが、
そのために、その音楽性に馴染めないひとには余計に異質な存在として捉えられ、
近寄りがたいと遠ざけられていた節もあったのではないか、とわたしは思っている。
ただし、これらマイナス面は意図されたものであった(と思うしかない)ことを、
いや、意図されたことの副産物だったのだと、あらためてここに言及しておきたい。
常識的に考えて、たとえ英語ができないからと言っても、あんな歌詞には絶対にならない。
ゆえに、それは意図されたものだ。ならば、理由があるはずである。
それも、上記の機能面だけではなく、表現したい「なにか」と関わるものが。
そして、その「なにか」に変化が起こった。だから「歌詞の変化」が必要となったのだ。
さて、ようやく、本論のスタートラインに立てた。
上記の歌詞観を前提に、新作について語っていくことにしよう。
まずは、#3-"In Scrying"から。長い間、新曲1と呼んできた曲だ。
昨年発表されたDVD『Delirium』にも収録された「ポップな」曲であり、
本作収録曲のなかでもっとも早い時点にできた曲である。(初演は水戸公演)
「明るさ」の大半は、80'Sを感じさせるリフとそのサウンドの印象に起因する。
本作の中ではもっとも「Anglish」的な歌詞である。とくにブリッジ(Bメロ)。
英単語自体は平易だが、言葉のリズムが英語的ではなく多分に「Anza的」なのだ。
BURRN!誌2011年8月号のインタビューでは「明るいのか暗いのかわからない」と言われていたが、
同誌今月号のインタビューで、この曲に触れてHiroは「底抜けに明るいコーラス」と言っている。
だが、わたしの印象は異なる。言葉がAnza的であることもあって、どこかしら不穏な陰りを感じる。
たしかに、『Delirium』所収のヴァージョンと比べるとさらに洗練され「明るく」なった。
ただ、Anglish独特の、言葉が溶け合うかのような音節の連鎖による認識の宙吊りや、
通常「リズミカル」と言うのとは違った趣きの「リズム」など、Anza的な磁場は強い。
「ポップすぎる」と外されそうになったらしいこの曲だが、おそらく理由はここにある。
要は、「Anza的=旧来のHPP的」な曲としては「ポップすぎる」のだと感じたのではないか?
逆に言うと、Anza的であっても、これまで通り「暗く重い」曲なら抵抗はないことになる。
それが#4-"Melt"~#5-"Dive"ではないのか。「気味の悪い」新曲3と呼んできた。
歌詞はもっとも単純な英詞となっている。その内容は「ラブソング」でさえあるのだ。
にもかかわらず、これはAnza語/Anglishによる「呪詛」であるかのように聴けてしまう。
歌い方に拠るところ大ではあるが、そう歌えるような音の単語が集められているとも考えられる。
リフは荒々しく、引き摺るようなヘヴィネスの密度は高い。ベースとドラムのグルーヴ然り。
ただ、これでも初めてライブでやってから数回のヴァージョンよりは聴きやすくなったと思う。
唐突に感じられた展開部も、案外すんなりと聴くことができた。気味の悪さはやや後退している。
それにしても、Anza語/Anglishではないのが信じられないほどのドロドロ感ではないか。
ただ、このヘドロはなぜだか厭な感じがしない。音作りの絶妙さが為せるわざかもしれない。
この2曲(3曲)は、言葉の響きにおいてこれまでのHPPと新しいHPPをつないでいる。
では、言葉の響きが変わったのはどの曲だったろうか。それはなにを変えたのか。
#7-"Just A Human"、#9-"Enter The Sky"、#11-"Rise And Shine"
の3曲をその例としてあげておこう。
これらの曲は、英詞が「ふつうの英語」になったことの恩恵をもっとも色濃く現している。
英語のリズムが自然になったことで、「歌詞の聞き取りやすさ」は格段に向上した。
また、そのリズムに乗るメロディもさらに明瞭になった。(曲自体は変拍子が多いが)
言葉が明確になったことで音節が画然とされ、それを受けてメロディもキャッチーになった。
つまり、同じメロディであっても、そこに乗る言葉が違うだけで印象は大きく変わるのだ。
ここでも逆に言うと、かつての曲の歌詞を変えると、これら3曲に似た曲となるものもあると思う。
(たとえば、『Prodigium』の曲の半分は歌詞の入れ替えが可能ではないか、と思っている。)
この文脈において言えば、これら3曲は旧曲の潜在的な可能性を明確な英詞で「開いた」わけだ。
「そうなっていたかもしれない」楽曲の姿を示したことで、却って旧曲に新たな光が当たった。
なぜ、かつてはAnza語/Anglishで歌われなければならなかったのか?
そう、それがAnzaにとって自然だったからだ。では、どう自然だったのか?
言いたいことを言うのではなく、どうしても言わねばならないことを吐き出すこと。
体外に排出しなければその身がもたぬ「なにか」、そんなものを明瞭にしておきたいだろうか?
だから、それは不明瞭でなければならなかったのだ。ゆえに、そう歌うことが自然だったのである。
Anza語/Anglishの機能についてはすでに述べた。歌詞の意味の陳腐さを、音楽的定型を避けること。
その内実はこうだったと思われる。あれはヴェールだったのだ。直視できぬ「なにか」を遮るための。
ヴェールで「なにか」を覆い隠す。それは、ある意味リスナーを「守る」ことでもあったかもしれない。
いや、それよりも、そうしなければAnzaが「もたなかった」のではないか。それは鎧でもあったのだ。
それほどまでに、その「なにか」は忌まわしく、憤ろしく、そして哀しい「なにか」であったに違いない。
だからこそ、あれ程までに張り詰めた音楽性となっていたのだろう。ライブにおいては尚更だった。
それはあまりに激しい独白だった。そこにはAnzaしかいなくて、他者は介在する余地がなかった。
同時に、Anzaは理解を求めはしなかった。理解を求めることは「なにか」を開示することだった。
それはできなかった。それ以前に、してはならないと思っていたのだろう。だから独り言となった。
だが、言葉には聞き手が必要なのである。たとえそれが誰にも理解されない言葉であったとしても。
この場合、Anzaの言葉の聞き手は、他ならぬAnza本人であった。
HPPのPVにおいて、Anzaはつねにその分身を登場させていた。黒と白。大人とこども。
あれはまさに象徴だったのだ。密室に籠り、自分にしかわからない言葉を紡ぐことの。
そして、プレビューライブのブログでも書いたように、そうした「密室」の時期は終わった。
自らを閉ざしていた密室の四壁は倒れ、あとに残された扉は開かれたのだった。広大な世界に向かって。
「なにか」を内に抱えていた少女は、それとは違う「なにか」を告げるため、開かれた扉から外へ出た。
#11-"Rise And Shine"をあらためて聴いてもらいたい。実に昂然とした曲だ。
歯切れよく言葉を繰り出すアジテイターのようなAnzaは、驚くほど「ロック然」としている。
そして、歌われる内容に括目してもらいたい。これは闘いの歌なのだ。自分を取り戻すための…。
本作には、そうした決意表明めいた歌詞が並ぶ。これまでは受け身だった倫理的葛藤から、行動へ。
内から外へ、閉塞から開放へ、ネガティヴからポジティヴへと、そのベクトルが180度転換したのだ。
#1-"Stand In The World"はこの「転換」の象徴であり、かつ契機でもあったろう。
新曲2と呼んできたこの曲は、新曲1と3の間にあって、まさにその中間点のような曲だった。
(実際、そういったバランスを意識して作られたのだとHiroが各誌で語っている)
リフには3に近い「硬さ」を、サビには1に近い、明るいのか暗いのかわからない「響き」を、
それぞれ感じていたのだったが、ライブで観るたびにアレンジが少しずつ変わってきたこの曲は、
最終的に広大なスケール感と柔らかな包容力をその身に纏い、決定的な曲として再登場したのだった。
語るべきところは多いが、タイトル・トラックに選ばれたことがすべてを物語っていよう。
明瞭になった歌詞と、そこに乗るメロディ。Anza語/Anglishの影は大きく後退した。
力強さは暴力的な攻撃性としてではなく、意志/意思からくる陽性のそれとして発現している。
かくして、HPPはそのスタンスを定め直すことに成功したのだった。
(本作のジャケットを見てほしい。これが現在の「立脚点」なのだ)
さて、こうなると「過去の総決算」が可能となる。
#6-"Where Are You"と#12-"Eyes"だ。
繰り返しとなるから、その内実について多くは語るまい。ここではその方法論に着目しよう。
いずれも、Anza語/Anglishではないところが最大のポイントであると言えはしまいか。
前者は、その構成から"Sixoneight"を強く想起させられる。ある意味「リメイク」とも言える。
優しげな前半はより優しく、激しい後半はより激しい。とくに、この後半部は過去最速ではないのか。
しかし、はっきりとその言葉が聞き取れるこの曲には、あの不明瞭さが醸していた厭な気配はない。
これまでとは違う「どこか」に到達したことを示す、記念碑的な曲となったように思う。
後者は逆に、過去の同系曲のような厭な気配に支配された「鬼の憑いた」曲そのままに聴こえる。
ただ、決定的に違うのは、ここでもやはり「歌」なのだ。叫びではなく「歌っている」のである。
過去の同系曲、"Alien Blood"や"Folie a Deux"といった曲は、
楽曲という鋳型に呪詛を流し込んで作っていたようなところがあった。
与えられた骨組みの上に、AnzaがAnza語でぶっきら棒に肉付けしていたと言うか。
これまでは「叫びのための場」にすぎなかった。それが、今回はちゃんと音楽になっている。
(もっとも、部分的にその激情が音楽という鋳型を決壊させているのだけど)
ちなみに、前半は22まで、後半はつづきから35までカウントを取っている。
Anzaの年齢だ。22は1998年のHPP結成時の、35はこの曲を書いたときの。
どれだけ意識していたのかはわからないが、こうした総決算的な楽曲を、
あらたに開拓した歌詞の方法論でもって更新したあたりにHPPの気概を感じる。
かくの如く過去を清算したら、未来に向かって歩めばよい。
文字通り、#2-"My Name Is"と#8-"Rainy Stars"はこの「未来」を扱っている。
いや、ロボットの一人称をとる前者はともかく、後者の舞台は未来とは限らない。
しかし、わたしにはこの2曲が舞台をともにする「姉妹曲」に聴こえるのだ。
同じ登場人物のいる、フィクションの世界が見えてくるのである。
前者はハードSF、後者はファンタジーのようだが、いずれも「少女」の影がチラつく。
それも、かつての「閉じた」少女ではなく、言うなれば「愛」の象徴としての少女が…。
楽曲も、フィクションのスタイルにぴったりと寄り添っている。
前者は「いかにもメタル」なリフが展開される曲で、近未来的なニュアンスに富んでいる。
しかし単純なメタルではなく、Narumiのベースが躍動することでヘヴィロック的質感が伴っている。
それはBatchのドラムにも言えよう。いや、全編にわたってこれは言えるのだった。
また後者は、個人的に「もっとも新しいHPP」だと思った曲である。
柔らかく優しげに歌われること(だけ)が目新しいのではない。
この曲の核にあるものこそ、HPPが目指す「なにか」に近似しているのではないか。
そう思ったのだ。直感したとも言える。"Light to Die"のような「明るい終末」を幻視する。
HPPは、「世界に愛を告げようとしている」のではないか。その世界が、たとえ崩壊寸前であったとしても…。
それはさておき、こうしたフィクションの世界など、これまでは考えられないことだった。
歌詞が「ふつうの英語」を介して客体化されたことで構造化し、却って表現領域が広がったのだ。
個人的な独白という「内向き」から、他者への語りかけ/三人称的他者として語る「外向き」へ。
陳腐化や定型化といったものを懸念する必要はすでにない。もしくは、元々なかったのではないか。
HPPの個性は、初期の時点ですでに揺るぎなく確立されていたと思う。『Vary』以降はとくに。
それでも「ふつう」を避けていたのは、内に秘めた「なにか」への後ろめたさのためだったか。
しかし、もう恐れるものなど何もないことに気づいたようだ。
ピアノとヴォーカルだけによる#10-"Lost Place"は、その証左ではないのか。
Anzaのソロキャリアに近い作風、と言うか、これをHPPとして発表したことに驚かされる。
このピアノバラードは、逆説的に現在のHPPが「何をやってもいい」領域に達したことを告げている。
言うまでもなく歌詞は明確だ。また、そこに込められた思いも。
象徴的な表現をとってはいるが、何を意味しているか、気づかれた方もいるはずだ。
ここ一二年の日本において「失われた場所」とさえ言えば、だれもがわかるだろう…。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
わたしが本作について思い、考えたことはだいたい以上のようなことである。
残念ながら、叙述の方向性と合致しなかったところは割愛せざるを得なかった。
とくに、歌詞論に集中したために音楽的なことに関してはあまり言えなかった。
ほとんど触れていない曲もあるし、長いわりには甚だ消化不良で情けない。
過去の楽曲との比較や、音楽的な細部のことなど、まだまだ言いたりないのだが…。
また、思っていることとややズレが生じたものもある。
これらすべては、わたしの力が至らなかったことによる。申し訳ない。
今回、語り切れなかったところは、おいおい書いていくことにしたい。
とりあえず、今回はこれまでとする。
.